英語の長文読解が苦手な高校生・中学生へ
「英語 長文読解 コツ」
「英語 長文読解 苦手」
「英語 長文読解 遅い」
「英語 長文読解 解き方」
などのキーワードで検索され、当ブログにご来訪いただき、誠にありがとうございます。
近年、大学受験における英語の長文読解が難化傾向にあり、リーディングスキルの向上がますます求められています。
このブログでは、長文読解を苦手としている高校生・中学生を対象に、その原因と対策を解説します。
英語長文読解はなぜ重要か?
本当の英語力は英文読解力で測れる
英語の長文読解力は、単に語彙や文法の知識だけでなく、その言語をどれだけ理解して使えるかを示す重要なバロメーターです。
英語がグローバルなコミュニケーションの主要言語である今、英文を正確に速く読解できるスキルがあらゆる場面で求められます。
近年の大学受験における長文の長さと傾向
大学入学共通テストをはじめとし、長文読解の文章は年々長く、複雑になっています。
また、国公立2次試験では、科学論文やデータを用いた問題が増えており、総合的な英語力を測るための出題がなされています。
基本的なアプローチで克服
英文の構造は結論が最後にくる日本語の文章と違い、結論が先に来て、その後に理由や例証が来る構造になっています。
また、長文を読む際は、全体の構造を捉え、重要な情報を効率的に取り出せる技術が必要です。
この基本的なアプローチをマスターすることが、長文読解力向上の第一歩となります。
このような基本的な知識があるだけで、たとえなじみのない内容の英文であっても設問に対処できる力がついていきます。
英語長文が苦手な人の問題点
英語の基礎力(語彙力、文法力、構文理解)の不足
多くの学生が、基本的な語彙や文法の知識が不足しているために、長文読解でつまずきます。
これらの基礎を固めることが先決です。
英単語については、大学入試共通テストでは約4,000~5,000語。
難関大学では、7,000語~10,000語とも言われています。
制限時間内に読み終わらない
長文読解では、特定の時間内に文章を読み終え、設問を解く能力が求められます。
2024年共通テストでは、約6,300語を80分で読み設問に答えることが求められ、そのためには150語/分の速度で読む能力を身につけることが、試験で成功するためには不可欠です。
ちなみに一般の高校生は75語/分が平均です。
内容は理解できるが、設問が解けない
問題の意図を正確に理解することと、文章から正しい情報を引き出すスキルが必要です。
しかし、多くの生徒が、読解技術を具体的に学んだ経験がないため、どのようにして効率的に読むかを知りません。
具体的な読解戦略を学ぶことが重要です。
これは練習と経験により向上します。
専門用語ではスキミング(文章の要点や大まかな意味を速く読んでつかむ技術)とスキャニング(必要な情報をできるだけ速く探す技術)と言います。
トピックスについての知識不足
特定のトピックや背景知識が不足していると、内容の理解が難しくなります。
幅広い分野に触れることで、この問題を解決できます。
最近ではAI、気候変動、エネルギー、食料問題など現在の社会問題などが出題されています。
復習をしない
一度読んだ文章や解いた問題を復習しないことで、同じ間違いを繰り返し、成長が停滞します。
復習には時間をかけ、理解を深めるべきです。
学校の英語の授業で予習をしていく人は多いですが、実際には予習以上に復習が大事です。
復習によって、授業で学んだことが定着し応用力に変わっていきます。
長文読解の基礎
長文読解問題の対策として上記のような問題をどのように解決していくか。まずステップバイステップで段階的に説明します。
次のような特徴を知っていれば、例えわからない単語があっても英文の流れをつかむことが可能な場合もあります。
英文の構造を知る
基本的な英単語や文法の知識があることを前提として、英文が速く読めない人の特徴は、英文の構造がわかっていない場合がほとんどです。
英文は前から読む!これが重要です。
返り読みをしてはいけない!!
つまり、基本的に何が、どうした、何を、どのように、どこで、いつの順番になっています。
そして、塊を意識しながら読み進むことが大事です。
どこまでが、主語で、目的語や副詞がどこまでか、スラッシュリーディングとも言われますが、この切れ目をきちんと理解できることで文構造がはっきりし、正確に英文を読むことができます。
段落構造の特徴を知る
英文の特徴がわかったら、長文の場合、いくつかの段落があると思いますが、その段落構成に注目します。
段落は新しい行から始まり、1つの段落に一つのトピックが書かれています。
通常は、段落の始めにその段落の内容をまとめたトピックセンテンス(キーセンテンス)があり、その後ろにそのトピックセンテンスの内容が書かれています。
各段落の最後の文は次の段落へのつなぎの文が書いてあります。
そして複数の段落の場合、各段落は、結論→理由→具体例→まとめ、概略→詳細、抽象→具象のような構造がほとんどです。
段落ごとに何が書かれているのかを意識して読む読み方をパラグラフリーディングと言い、長文読解の場合、段落同士の関係を考えて読むことが大変重要です。
段落と段落はディスコースマーカーと言われるつなぎ語で結ばれています。
「しかし」でつながれていればその段落同士は逆接関係にあるとか、「例えば」であれば例示になっているなど、話の流れを示す「接続詞」「指示語」などディスコースマーカーに注目すると話の流れが見えてきます。
単語を予測する力
英文を読んでいて未知の単語に出会った時、辞書を引くことは確かに重要ですが、前後関係から意味を推測して読んでいくことも大事です。
試験ではもちろん辞書を使うことはできませんし、大量の英文を速く読む際にいちいち辞書を引いていては読み進みません。
文脈や単語の形状から単語の意味を予測できることが英語長文読解において大きな差を生みます。
長文読解のスキルを身につけるトレーニング方法
語彙力・文法力をつける精読
英検®2級レベルまでは、複雑な長い文構造の文は前からスラッシュを引き、文の構造を把握し
単語の意味を一つ一つ確認することが正確な英文読解につながります。
概要をつかむ速読
精読がある程度できるようになったら、精読と同時に速読を行なうことで、先に述べた段落や文章全体の要点をつかむ訓練が必要です。
その際には必ずWPM(一分間に何語読めたか)を記録することが大切です。
精読と速読をバランス良く学習に取り入れることが、長文読解を正確に効率よく行えるようになる鍵です!
時間配分
テストなどの長文読解は全体の時間から各問題の時間配分を行なって、日頃から時間配分に配慮して問題を解く訓練を行なうことが大切です。
適切な時間配分を身につけることで、テストの際にもパニックに陥ることなく、計画的に問題を解くことができます。
設問の先読み
選択式の問題では特に、どこに答えの根拠があるのかを探す必要から事前に設問に目を通しておくことで時短ができるだけでなく、内容を予測しながら読めるので読解が容易になります。
音読
復習として意味がわかった英文を何度も(最低5回)音読することで、意味と英文が頭の中で一致し、英語から日本語への変換が飛躍的に速くなります。
これを繰り返していけば自動的に英文が日本語の意味と結びつき、最終的に英文を読むことが爆発的に速くなります。
音読はまた、発音の練習にもなり、実際の会話やリスニング能力の向上にもつながります。
大学受験英語:長文読解の技術と戦略
大学受験における英語長文読解の能力は、成功への鍵です。
一般に、読解問題としては500語程度の文章が出題されますが、最近の試験では、さらに長い700〜1000語の文章を読み、設問に答える問題が増えています。
これらの文章は、最新の科学的トピックや専門分野に深く踏み込んだ内容であり、複雑なデータや理論を解釈することが求められます。
このため、速読と精読を組み合わせた読解技術が非常に重要となります。
速読で文章の全体構造と主要なアイデアを捉え、精読でその詳細を深く理解することが、効率的かつ効果的に問題を解決する鍵です。
時間は限られているため、前に述べた技術を駆使して情報を迅速に処理する能力を身につけることが必須です。
また、受験する大学の過去問を徹底的に分析し、その大学の出題傾向と特徴を理解することも、戦略的な学習計画を立てる上で欠かせません。
大学によって出題されるテーマや形式が異なるため、それらを踏まえた上で適切な読解戦略を編み出すことが、合格への道を切り開くことにつながります。
残念ながら長文読解のスキルについては学校であまり教えられることがありません。
このブログは、読者が英語長文読解のスキルを効果的に向上させ、大学受験に自信を持って臨むための支援を目的としています。
習得すべき技術を身につけ、試験に挑む準備を整えましょう。
投稿者プロフィール

- 英検®対策のオンライン英語塾
-
英検®対策専門のオンライン英語塾です。
レッスンは、マンツーマンで完全個別指導。
英検®1級、TOEIC950以上のプロ講師が2次試験対策も丁寧にサポートします。
『読む・聞く・書く・話す』の4技能を養い、英検®合格を確実に達成しましょう!
最新の投稿
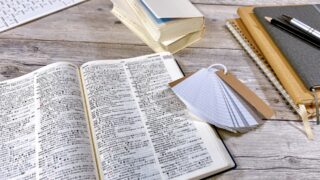 BLOG2024年6月24日英単語の効率的な覚え方について
BLOG2024年6月24日英単語の効率的な覚え方について BLOG2024年6月9日リスニングが苦手な理由と克服法について
BLOG2024年6月9日リスニングが苦手な理由と克服法について BLOG2024年6月1日英検®取得は総合型選抜で有利になる
BLOG2024年6月1日英検®取得は総合型選抜で有利になる BLOG2024年5月14日英語の長文読解が苦手な高校生・中学生へ
BLOG2024年5月14日英語の長文読解が苦手な高校生・中学生へ



